【質問紙の構成:余談】:自分で作ったアンケートは尺度として使えるか?
結論から言うならば、使えないことがほとんどです。例えば映画の感想を聞くアンケートを考えてみましょう。
☑この映画は楽しかったですか?
☑この映画はハラハラしましたか?
☑この映画でバイブスはあがりましたか?
これらの質問項目が並んでいたとして、この映画の楽しさを正しく測れているといえるでしょうか。「楽しい」も、「ハラハラ」も人によってイメージは違うかもしれません。「バイブス」については意味の分からない人もいることでしょう。また3日後にアンケートを取った場合にほぼ同様の結果になるでしょうか。
心理学における尺度は「妥当性」と「信頼性」というものを兼ね備えていないといけません。「妥当性」とは測りたいものが正確に測れているかどうかです。映画の例でいうと「映画の楽しさ」が正しく測れる質問項目になっているかどうかです。「信頼性」とは何度尺度をとっても同じような結果になるかどうかです。映画のアンケートの場合は「3日後にアンケートを取った場合にほぼ同様の結果になるかどうか」です。一般的に、妥当性が高ければ信頼性も高いです(逆は言えませんので注意が必要です)。
自分で作ったアンケートは、妥当性と信頼性が担保されていないので分析で使用するのが難しいです。ですが、「客観的事柄を数値で尋ねる項目」であれば分析においても利用できると考えています。例えば以下のような項目です。
☑昨日自動販売機でジュースを何回買いましたか?
☑この一週間一番親しい家族と何件のメッセージをやり取りしましたか?
☑昨日の食事の回数は何回ですか?
客観的な数値であれば、体重や身長、心拍数や血圧なども利用できます。もう少し学術的な説明をするのであれば、構成概念と呼ばれる人為的に作り出した概念ではなく直接測定可能なものであれば用いることができます。
装置
実験を行う場合は記述する必要がありますが、質問紙調査などでは記述しないことがほとんどです。一応、記述例だけ載せておきます。
装置
実験箱:30cm(高さ)×30cm(幅)×30cm(奥行)の透明なケースに給餌機を装着する。外側にあるレバーを引いているときに、給餌機のボタンを押すとエサが排出される。
手続き
どのような手続きを踏んでデータを取得するかということについて記述します。介入実験などにおいては非常に重要になりますので丁寧に記述しましょう。質問紙による量的研究では重要度は下がりますので、字数制限によっては省略または簡潔に記述するようにしましょう。分析のやり方まで記述して、後述の「分析」の項目を省略してしまうという記述をする方もいます。
ここでは、「群分け→事前質問紙→介入→事後質問紙」という事例を想定して記述してみましょう。
手続き
実験参加者に本研究の説明を行い同意を得る。なお、この同意はいつでも取り消すことができ、取り消したとしても何の不利益もないことを説明する。同意を得ることができたら、不安に対する尺度(寺島,2022)に回答をしてもらう。その後、コンピュータによる乱数を用いて介入群と統制群に分ける。介入群には別の部屋に移動してもらい、1時間の呼吸法訓練を受けてもらう。統制群は室内にて自由に過ごしてもらう。1時間経過後、再度不安に対する尺度(寺島,2022)に回答してもらう。倫理的配慮
実施前に倫理審査委員会の承認を得るものとする。実験中は救護スタッフを常駐させ不測の事態にも対応できるようにする。
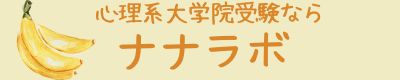
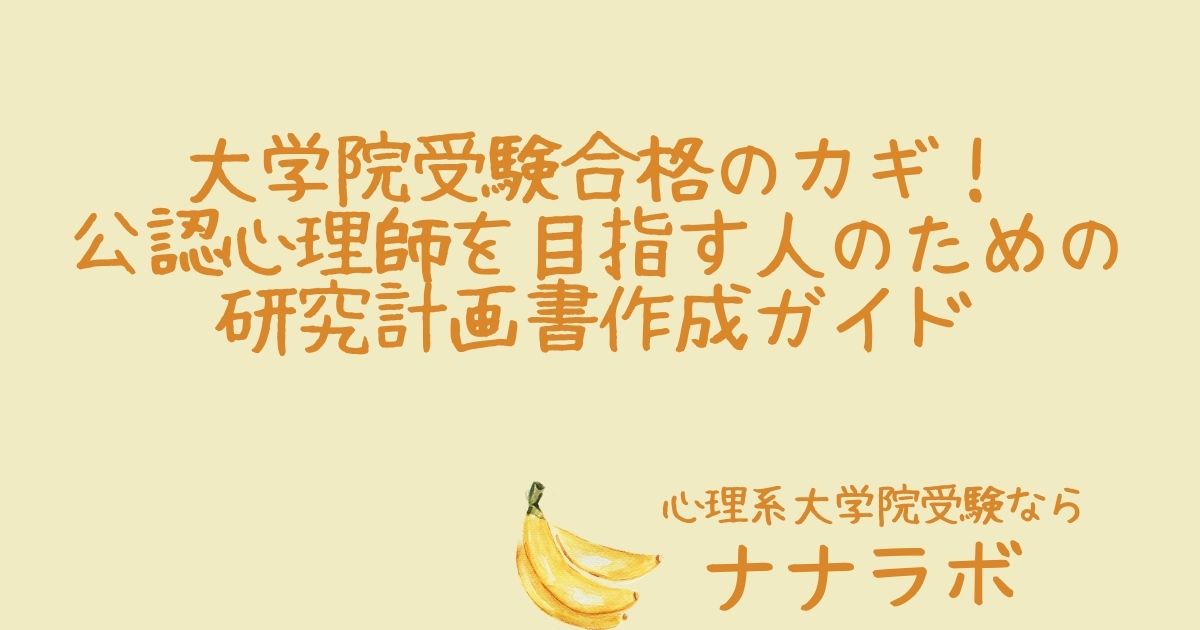


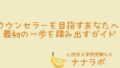
コメント