分析
方法論における目玉となる部分の記述になります。しばしば見かけるのは以下のような例です。
分析
得られたデータに対して統計的分析を行い結果を考察する。
これでは、足りないことが多すぎるので大幅な減点は免れないと考えます。分析において重要なのは「研究目的」をここに書かれている「分析」を行えば達成できるのかどうかです。上述の例は「得られたデータ」の詳細と、「統計的分析」の詳細がわからないため研究目的を達成できるのかどうかがわかりません。質的研究の場合は統計的ではありませんが、構造化された分析手法を用いることになります。質的研究の場合も「得られたデータ」と「分析手法」について明記することが必要です。
例えば、ある心理療法を実施する前に不安の尺度を取り、実施後にも不安の尺度を取った場合はその効果を知りたいということになりますので実施前と実施後の尺度の得点をt検定により統計的有意であるかどうかを分析します。
分析(量的研究の場合)
実験参加者50名の心理療法実施前における不安尺度の得点の平均値と心理療法実施後の不安尺度の得点の平均値を参加者内計画によるt検定で比較する。
分析(質的研究の場合)
実験参加者にインタビューを行い、その内容を逐語録に起こしたものを分析対象のデータとする。得られたデータをM-GTAを用いて分析し、モデル構築を行う。
研究目的で仮説生成がされている場合は、仮説の検証が可能な分析方法を設定しなければなりません。挙げた例はどちらも分析を一回しか行わないものですが、複数の分析手法を用いる場合はすべて記述する必要があります。
この部分は研究目的によってどのような手法を用いるのか大きく異なります。また、研究目的がすべて明らかになるような分析方法を設定しなければなりません。初めて研究計画書を作られる方の多くが、研究目的と分析手法の整合性がとれておらずちぐはぐな研究計画書になってしまっています。
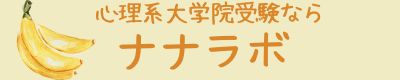
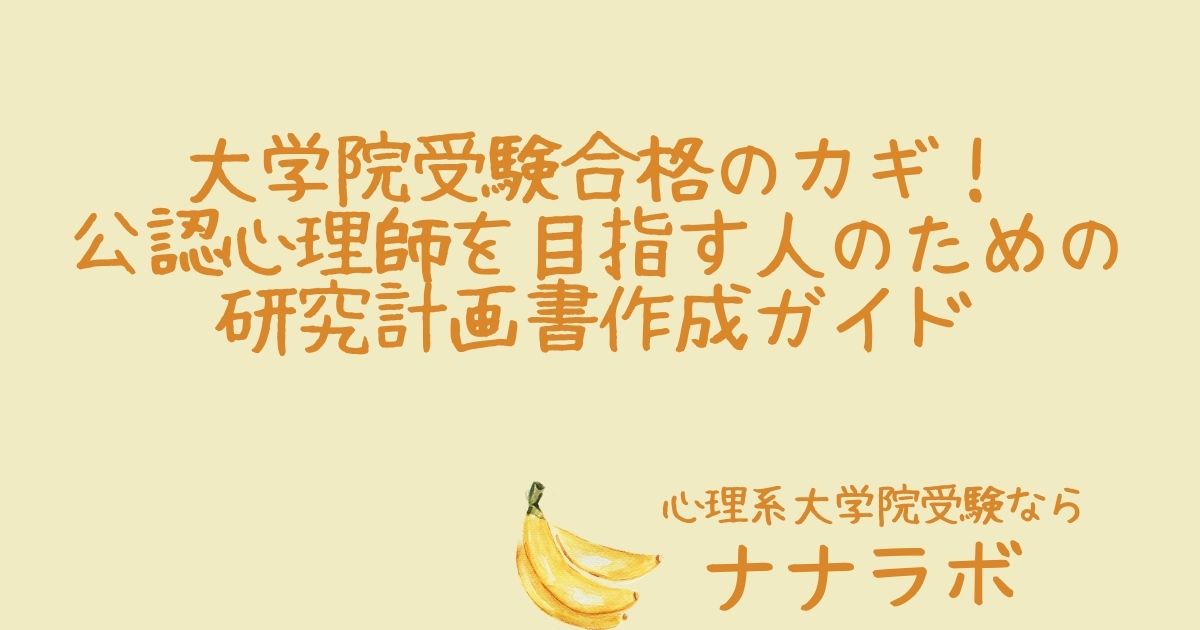


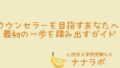
コメント