1. はじめに
公認心理師を目指すなら大学院進学が重要
公認心理師試験の受験資格を得るためには、大学の卒業が必須です。大学受験は予備校や教材も多く勉強に困ることはありません。また、通信制の大学であれば筆記試験を課していないところもあります。大学院に行かずともプログラム施設に就職できれば公認心理師の受験資格は得られますが、プログラム施設は2025年現在非常に少なく、就職するのは至難の業といえます。
つまり、公認心理師の受験資格を得るには大学院に進学することが最も現実的なのです。しかし、大学院入試は情報が少ないため、どのように勉強をすればいいかわからないですよね。
この記事では公認心理師の受験資格を得られる大学院の筆記試験の勉強方法について解説します。
筆記試験は「心理学」と「英語」がカギ
心理系大学院の入試は「専門試験」「外国語」「口頭試問」という三本柱で行われるところがほとんどです。専門試験は学部で勉強する範囲で心理学の問題が出題されます。これは心理学研究法つまり、量的研究や質的研究の手法についても問われます。簡単に言うと統計関連の知識も必要になります。外国語は中国語やドイツ語などが選択できるところもありますが、多くは英語を選択することになるでしょう。
筆記試験は「専門試験」と「外国語」によっておこなれることになりますので、心理学と英語をいかにマスターするかということが筆記試験突破のカギとなります。
独学でも合格は可能!効率的な勉強法を解説
最近では心理系大学院の予備校も増えてきています。ナナラボをはじめ心理系大学院の予備校は多くの情報を日夜集めています。公認心理師制度が始まってから心理系大学院の合格率は年々厳しくなってきております。しかし、だからと言って予備校に行かなければ合格できないかといえばそういうこともありません。
正しい方向で十分な努力をされれば、独力でも合格することはできます。現に私の受験相談のサービスのみを使い後は独学で合格されたという方もいます。
独学で合格を目指す場合、一番重要なのは志望校の選定です。なぜならば、定員の多くを内部推薦者で埋めてしまい外部受験者はほとんどとらないという大学院も中には存在します。そのような学校を単願で受け続けていも合格するのは困難でしょう。
予備校を使わず独学での合格を目指すにしても、予備校の受験相談は必ず受けたほうがよいでしょう。
過去問から見る出題傾向
公認心理師の資格取得を目指して大学院受験を考えている方にとって、筆記試験の内容や傾向を知ることは、効果的な対策を立てるうえで重要です。大学院の筆記試験では、主に「心理学」と「英語」が出題されますが、その内容や難易度は大学院ごとに異なります。中には小論文のみ、口頭試問のみという大学院もありますので、まず自分の志望校がどのような形式なのかを募集要項を見て調べましょう。
心理学
心理学の試験では、大学学部レベルの心理学の知識が問われます。出題形式は大学院によって異なりますが、以下のようなパターンが一般的です。
- 論述式(記述式):心理学の概念や理論について、自分の言葉で説明する問題。
- 選択式(マーク式):基本的な心理学の知識を問う問題。
- 計算・統計問題:心理学統計や研究法に関する問題(t検定・分散分析など)。
出題範囲
試験範囲は大学院ごとに異なりますが、一般的には以下の分野から出題されることが多いです。単元については、教科書によっても異なるのでここに示した表は一例に過ぎません。また、すべての分野から満遍なく出題するという大学院は少なく、たいてい出題分野は偏っています。
| 出題分野 | 主な内容 |
|---|
| 基礎心理学 | 知覚・認知、学習、記憶、感情、動機づけ、神経心理学 |
| 発達心理学 | 乳幼児から高齢者までの発達過程、愛着理論、発達課題 |
| 臨床心理学 | 心理療法(認知行動療法、精神分析など)、精神疾患、心理アセスメント |
| 社会・人格心理学 | 社会的認知、態度、対人関係、パーソナリティ理論 |
| 犯罪心理学 | 犯罪の心理的要因、非行・逸脱行動、矯正プログラム、リスクアセスメント |
| 教育心理学 | 学習理論(ピアジェ・ヴィゴツキーなど)、教育評価、動機づけ、発達支援 |
| 心理統計・研究法 | 基本的な統計手法、研究デザイン、心理測定法 |
最近の傾向
大学院によってかなり違いがあるということは大前提ですが、全体の流行のようなものは存在します。2025年現在の流行は、心理学研究法をほぼ必須にしてきているということでしょう。これに関しては心理系大学院の予備校の中ではほぼ共通認識と言ってもよいのではないでしょうか。
専門用語の説明問題に関しても、ほぼ必須といえます。これは以前から変わりません。大門としては、①用語説明、②心理研究法という二つは確定で出題され、3つめに事例を出す学校と、各分野の踏み込んだ論述を出してくる学校に分かれるという印象です。事例を出題してくる学校が増えてきたように思っています。論述の場合も臨床心理分野から出題する傾向が高いと感じています。例えば「インテーク面接の際に留意する事項」や「集団守秘義務」といった臨床現場で必ず必要になる現実的なテーマが多いです。公認心理師制度が始まり、実務に特化にした心理師が求められていることが反映しているのかもしれません。
英語
過去問を取り寄せても、英語は著作権の関係で公開されていないことがほとんどです。なので、その全体的な傾向をつかむことは難しいのです。しかし、受験生の聞き取りや私の体験を踏まえて予測するならば、多くの大学院が心理学の英語論文を読解させるという方法をとっているでしょう。長文読解ですので、基本的には大学受験の長文読解用の参考書が役に立ちます。
しかし、語彙についてはかなり専門的なものになりますので、心理学の英単語を覚えるという必要があります。英語に関してその指標を示すのはかなり難しいですが、TOEIC L&Rで700点以上取ることができれば英語の基礎的な能力は大丈夫と言えるでしょう。
これまで社会人の方を多く教えてきましたが、合格された方のほとんどは英語が堪能であったり、英語の勉強に一定時間を割かれていた方です。英語の出来が勝敗を分けるといっても過言ではありません。
多くの大学院の募集要項を見ても、専門試験とあまり配点が変わりません。専門試験は皆さんしっかり勉強してくるので差が出にくいですが、英語は差が出やすいです。しっかりと対策を行いましょう。
各大学院ごとの特徴をチェック
大学院によって傾向がかなり異なってくることは前述していますが、中でも人気の高い大学院の傾向を簡単に触れておきましょう。
放送大学大学院
ほぼ臨床心理学の分野からしか出題されないといっても過言ではありません。ただ、英語の試験がないため英語の専門用語を説明させるということが以前ありました。出題傾向もほぼ固まっており、臨床心理士の専門性である①面接、②査定、③地域援助、④研究になぞらえて出題されることが多いです。知識があれば完答できる問題から、臨床的なセンスを要する問題まで様々な形で出題されます。大門5つというのが例年の傾向です。知識でこたえられる問題をいかに完答するかがポイントでしょう。そこまで難しい問題は出ない上に、範囲も臨床心理学と研究法に限定されていますので、知識問題をこたえられないとかなり不利になると言わざるを得ません。
東京大学大学院
センスを問うような問題ではなく、知識が入っていれば確実に解ける問題を出題してくるというあたりに最高学府の矜持を感じます。ただし、かなり細かいところまで聞かれますので、基礎心理学と臨床心理学、教育心理学、心理学研究法においてはかなりの水準で理解していることを求められます。質的研究に関して細かいところまで問うてきたり、量的研究においては計算や証明が出題されたこともあります。
「統計は苦手なので捨てる」という方を頻繁に見ますが、これをやるとまず受かりません。経済学部や理系学部と同様の水準で統計学を理解する必要があります。
【心理学】筆記試験の勉強法とおすすめ参考書
よく言われることですが、学習はインプットとアウトプットに分かれます。インプットは書籍などを読み知識を蓄えていくこと、アウトプットは演習を通して知識を定着させたり応用させたりすることです。当然のことながらインプットなくしてアウトプットはありません。つまり、最初はひたすら本を読むという作業になります。
「本を読むのが苦手なので動画などはありませんか」と聞かれることが多いですが、本が苦手な方は間違いなく予備校に行かないと受からないでしょう。心理学の知識は専門性が高いため、良い動画配信者がいないというのがその理由になります。
独学で受かるには本を読むことが必須です。しかも内容が一般書籍に比べて難しいので2回3回と読む必要があります。大学院受験においてまず読むべき本をご紹介します。
ヒルガードの心理学
基礎心理学は、この本に書かれている内容がすべて頭に入っていればどの大学院でも合格水準に達することができます。臨床心理学なども一部記述されていますが、あくまでも基礎心理学の教科書だと考えてよいでしょう。放送大のような臨床心理学しか出ないという場合は、少し詳しすぎる本かもしれません。逆に東京大学などを受験されるのであれば、書かれている内容でわからないことはないようにしておきたいですね。自分の大学院がどの程度基礎心理学の知識を求めてくるかによって買うか買わないか迷う本です。
心理学 第5版補訂版
心理学の代表的な教科書です。基礎心理学においては全体像を俯瞰することができます。読みやすく2-3日で読み切れますが、内容的には少し足りません。もう少し詳しく説明している教科書をもう一冊マスターしておく必要があるでしょう。
ただ、最初に読むには非常に良い本です。例えば、いきなりヒルガードの心理学や有斐閣の心理学の基礎知識などを読むと少し難しく感じるかもしれません。先にこの本を読んでおけば次に読む本の理解が容易になります。
「よし!大学院に挑戦しよう」と思ったらまず読んでおきたい本です。
DSM-5-TR
必携です。精神疾患系の論述や用語説明が出た場合にはDSMに沿って回答することが求められます。できればこちらの方が良いですが、お金がない場合などは短縮版の薄いものでも構いませんので必ず手元に置くようにしてください。頻出診断名については、診断基準を暗記してもよいと思います。
これからの現場で役立つ臨床心理検査【解説編】
大学院受験においては、心理検査に関する知識が必須です。しかしながら、心理学の教科書には意外と検査のことは乗っておらず、教科書だけで学習していると検査に関しての理解が追いつきません。公認心理師用の受験本には書かれているのでそちらでもよいのですが、幅広い検査を概説しているこちらの本もよいです。現場で使われているものがほとんどなので、実践的な公認心理師を要請するという大学院の立場からもニーズが一致している本だと考えます。
臨床心理学 (New Liberal Arts Selection)
心理療法と各疾病に関する支援に関しては非常に丁寧に書かれています。上述したDSMと現場で役立つ臨床心理検査を手元に置きながら読み進めていくのが良いでしょう。臨床心理学においては、この本と上述した二つの本でかなりの範囲をカヴァーできると思います。
【英語】筆記試験の勉強法とおすすめ参考書
英語の学習は英語の基礎があると仮定するならばひたすら英文を読んでいくのが良いです。ただ、英語の基礎(TOEICで700点程度)がないのであれば、まずは英語の基礎を学習していく必要があるでしょう。
The Psychology Book (DK Big Ideas)
英語の心理学の教科書です。大学で使う専門的なものというよりは一般書籍に近いでしょう。図がたくさん載っており短いので心理学系の文章に親しむのにはうってつけといえます。内容がすらすらと入ってくるのならば大学院受験の準備は整っているといえるでしょう。
一生モノの英文法 COMPLETE MP3 CD-ROM付き
遠回りのように感じるかもしれませんが、英文法の基礎が出てきていないのであれば英文法をしっかりと学ぶことをお勧めします。私は英語学習が趣味なのでいろいろな文法書を読んでいますが、おそらくこれが最も全体を網羅しており、最もわかりやすい文法書です。「単語に終わりはないが、文法には終わりがある」とよく言われます。英語の基礎が足りない場合は英文法を終わらせましょう。
心理院単
大学院受験の英語における必携書です。院試では専門的な英文を読まされることになりますので、かなりの語彙力が要求されます。心理学の専門用語を一通り網羅した本ですのでこれをすべて暗記しておけばかなりの武器になるでしょう。
まとめ
公認心理師の受験資格を得るには大学院進学が重要です。大学院入試では「専門試験」と「英語」がカギとなります。心理学の試験範囲は基礎心理学、発達心理学、臨床心理学など多岐に渡り、統計や研究法の知識も必要です。英語は心理学の英語論文読解が求められ、専門用語の習得が重要です。独学で合格するには、志望校選定と効率的な学習が必要です。おすすめの参考書には、基礎心理学に強い『ヒルガードの心理学』や英語の専門用語を網羅した『心理院単』などがあります。
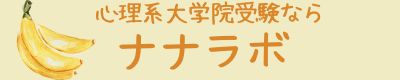
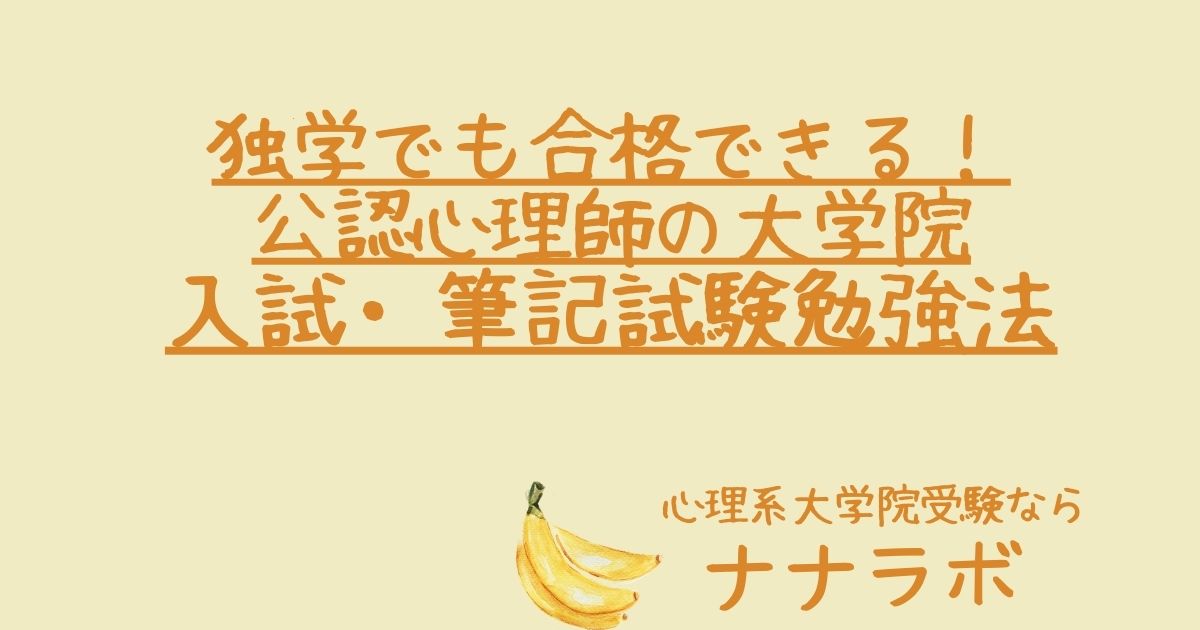

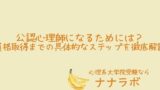
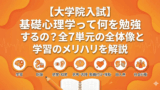
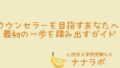

コメント